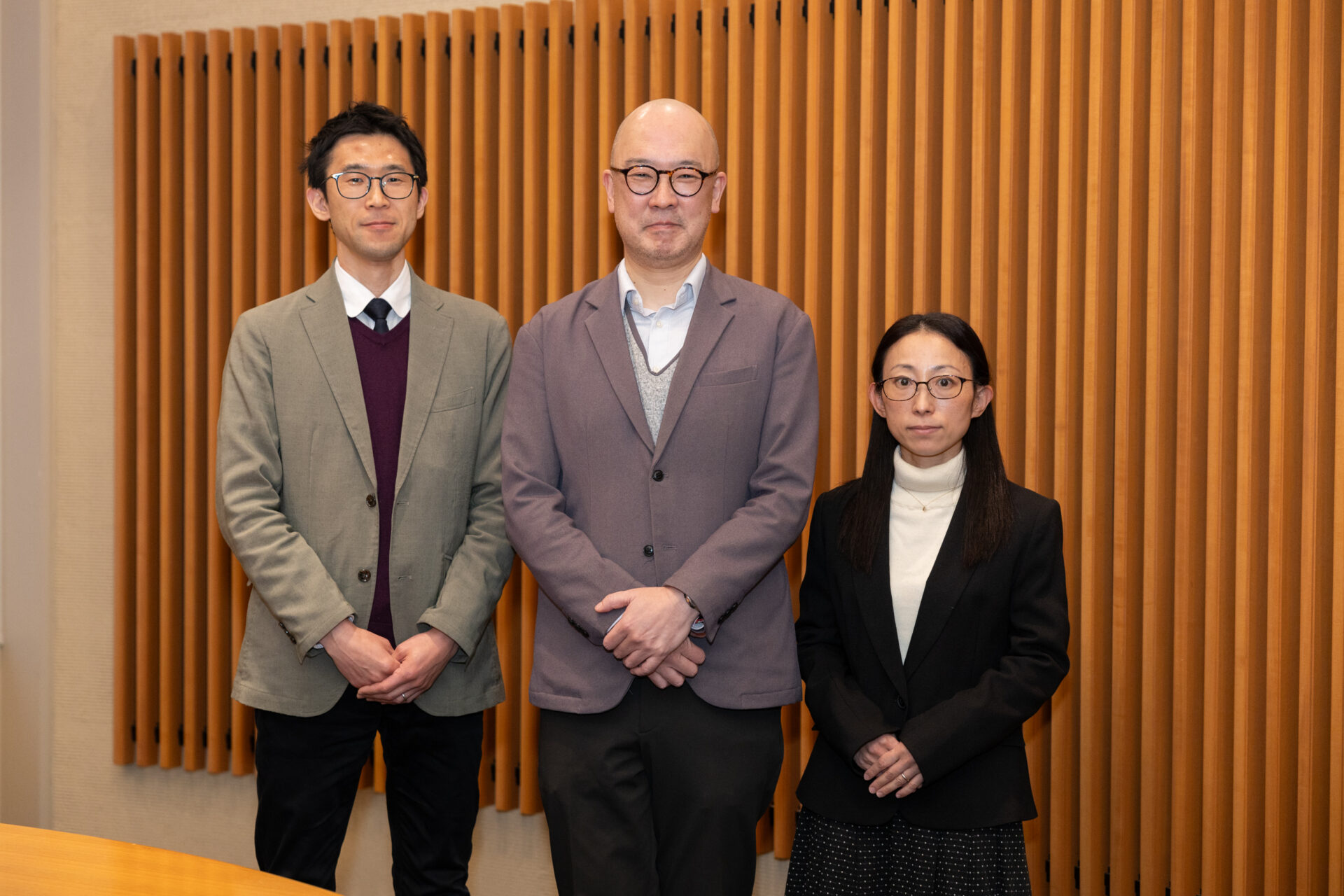学生の成長を可視化し、教育改善を自走させる東洋大学の挑戦
-
学修成果MOE
-
退学防止・学生フォロー
-
データ活用・可視化
-
業務効率化
東洋大学

-
導入時期
2018年
-
概要
◆導入検討のきっかけ
全学的な質保証と教育改善に必要な“学修成果データの不足”を解消するための、本格的な可視化基盤の整備
◆導入の決め手
大学の理念や複雑な学部構造を深く理解し、“一緒に仕組みをつくる姿勢”で伴走してくれた点
◆導入後に見られた変化
自己点検に必要なデータが全学で整備され、学生・教員双方の学修成果活用の促進
◆運用・活用における工夫
標準化と学部独自性を両立させる運用設計により、多様な学部が自らの教育改善に主体的に向き合える環境の整備
interview
MEMBER
参加者
-
副学長 / 高等教育推進センター長
澤口 隆 様
-
学長室学長事務課 / 高等教育推進支援室
課長
新山 文洋 様
まずは学修成果の可視化に取り組まれた背景を伺えますでしょうか?
新山様:
本学では、2017年ころに学内で学修成果の可視化と活用についての検討会を発足しました。本学は14学部を有し、専攻単位まで含めると50を超える構造です。しかし当時は、自己点検評価に必要なデータが全学では揃っておらず、学修成果を議論するための“起点”が整っていませんでした。
2017年以降、学修成果をどの指標で測定するか、学部の独自性をどう扱うかなど、土台となる議論が求められていました。とくに2021年度認証評価を控えていたこともあり、単に制度対応としてではなく、“大学として教育改善と質保証の仕組みをどう整えていくか”という中長期視点で準備を始めた形です。
澤口副学長:
学修成果は、教育の「結果」を見るだけではなく、「改善の出発点」をつくるものです。
ですが、当時は教員が持つ成績データや学部ごとに蓄積してきた指標が全学で一元化されておらず、改善のための議論が十分できる状況ではありませんでした。
“データがなければ議論が始まらない”その課題感が、本格的な可視化検討の起点でした。

学内ではどのように検討を進めていかれたのでしょうか?
新山様:
学長の方針のもと、副学長を中心としたワーキンググループを立ち上げました。
高等教育センター、教務部門、各学部の教員が集まり、学修成果指標をゼロから議論しました。
・GPAを基軸にする妥当性
・DP(ディプロマ・ポリシー)との対応関係
・数値で測れない学修成果の扱い
・学部独自の指標をどのように反映するか
文系・理系、学部規模、学科文化が違えば、成果の捉え方も異なります。
そのなかで共通の枠組みをつくる作業は非常に丁寧な検討が必要でした。
澤口副学長:
教授会にも足を運んで説明しましたが、「文系の学びを数値化できるのか」「理系の成果とは異なるのでは」といった率直な意見もたくさんありました。しかし、実はこの議論こそが質保証の本質でもあります。
大学基準協会の研修でも、学修成果の可視化は、フォーマットを作ることではなく、議論のプロセスそのものが重要だと言われます。各学部が「自分たちの教育で何を成果とみなすか」を改めて考える機会になりました。

数ある選択肢の中で、当社を選ばれた理由を教えてください。
新山様:
本学ではまず、何を可視化し、どう教育改善につなげたいのかという理念を明確にし、その構想を共に実現できるパートナーを探しました。当時、市場には十分な解がなく、既存システムを選ぶというより、大学の意図に合わせて一緒に仕組みをつくり上げてくれる企業かどうかを重視しました。
ハーモニープラスは、仕様が固まっていない段階から議論に伴走し、学部独自指標の扱い、DPをどこまで要約し学生にどう見せるかといった、大学の教育思想に踏み込むテーマにも真摯に向き合ってくれました。
また、学部の多様性や規模、現場の負担感といった本学固有の文脈を深く理解しようとし、議論で生まれた内容を何度もプロトタイプに落とし込みながら方向性を確かめていく姿勢が印象的でした。
大学のやりたいことをどう実現するかを同じ目線で考え、最後まで伴走してくれる——その確かな姿勢こそが、最終的な選定の決め手でした。
澤口副学長:
学部や専攻ごとに事情が異なる大学組織では、検討を進める中で想定外の論点や条件変更が必ず生じます。そのたびに、背景を理解したうえで柔軟に対応し、継続的に支えてくれるパートナーであることが極めて重要です。
ハーモニープラスは、単に「できるかできない」を提示するのではなく、大学の意図をどのように形にするかを常に一緒に考え、必要な調整を根気強く積み重ねてくれました。多様な学部・専攻を抱える本学にとって、その姿勢は大きな安心材料でした。
結果として、本学の教育方針を踏まえ、それに沿った形で仕組みを作り上げてくれる確かな伴走力が、最終的な選定の決め手になりました。

当社システムを導入いただいた後、どのような変化がありましたか?
新山様:
まず、全学で自己点検に必要なデータが整備され、GPAやDP対応状況などの指標を同じフォーマットで提示できるようになりました。これにより、エビデンスが揃い、議論の座組みそのものが変わりました。
さらに、学部の議論から生まれた独自指標を正式に反映できる仕組みが整ったことで、標準化と学部固有性の両立が可能になり、学生の成績や成果をもとにカリキュラム等を検証する文化が芽生えてきています。
加えて、データが可視化されることで “もっと深く見たい” という声が自然と生まれています。入試方式別の傾向、専攻横断での学年推移、教材導入の効果など、議論が教員側から広がり、教育改善のサイクルが自走し始めていると実感しています。
澤口副学長:
学生にとっても変化があります。
レーダーチャート等を通じて自分の学びの位置づけを確認できるようになり、成績を見ながらDPを自然に意識する場面が増えています。
こうした可視化が、学生・教員双方にとって“教育改善の起点”となり、大学全体の質保証を支える基盤になりつつあります。
大規模大学ならではの気づきはありますか?
澤口副学長:
大規模大学は合意形成に時間がかかります。そのため、可視化の導入も複雑になりがちですが、学修成果に向き合うプロセスそのものが質保証の核心であることを忘れないことが重要です。
新山様:
どの規模感の大学でも同じ課題があると思います。
「データが揃わないと議論が始まらない」という本質は規模に関係ありません。
可視化は大学が次のステージに進むための“共通言語”になると感じています。

最後に—今後の取り組みについて教えてください。
新山様:
学修成果は数値化できるものだけではありません。主体性や探究心といった、定性的な「見えない成長」をどう捉えるかが、今後の重要なテーマです。
また、2025年度からの授業期間短縮(13週化)によって生まれる4週間を、いかに学生の主体的な学びに転換できるか。ここにも学修成果可視化の知見をフルに活かしていきたいですね。
澤口副学長:
可視化を単なる仕組みで終わらせず、大学の“文化”として根付かせることが最終的な目標です。
システムはあくまで手段に過ぎません。大学全体が主体的にデータと向き合い、教育改善のサイクルを回し続けることこそが、本質的な大学改革につながると信じています。

この事例は以下のサービスをご利用いただいています

contact
ご興味をお持ちいただいた方へ
-
資料請求
サービスの詳細や導入事例をまとめた資料を
ご用意しています。 -
お問い合わせ
導入相談・お見積もりなど、
お気軽にお問い合わせください。